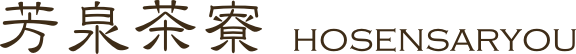芳泉茶寮のパイナップルケーキ
Date:Mar 29, 2019 (Fri)

芳泉茶寮の開業と同時に、みなさんからご注文をいただいたパイナップルケーキ。
最初は1回12個ぐらいを焼いていましたが、今は1単位32個を週に5-6回焼くのが通例となりました。
販売開始して2年半で、販売個数10,000個となりました。
みなさま、ありがとうございます♪
みなさんに愛していただいているパイナップルケーキについて、ちょっと書きたいと思います。
パイナップルケーキの記憶
台湾のお土産と言えばまず思い浮かぶのがパイナップルケーキ。
初めて食べたのは子供の頃。美味しいお菓子だなあ、という記憶が残っています。
パイナップルケーキの記憶
台湾を初めて訪れたのは25歳の時。凍頂烏龍茶に初めてであったのもこの時でした。
子どもの時に食べた記憶のあるパイナップルケーキ。
好きなんだけど、食べた後にずっしりと重くて、甘くて。
この先、自分好みのパイナップルケーキを模索していくことになるとはこのころは露知らず。
点心学校に通って、点心を作るように
2004年、2005年と信博さんの転勤で上海に住むことになった私たち。
私が中国でやりたかったこと、それは飲茶の点心を作れるようになりたい!ということでした。
全く中国語が出来ないまま、どうしても学校に通いたくて、必死に検索して、
学校に足を運び、筆談で何とか意思疎通して授業開始の日に生徒として認識してもらいました(笑)。
点心師初級クラス。水餃子から始まり様々な形の蒸餃子やパイ菓子、
お饅頭などを作りましたが、授業の中で「鳳梨酥」というメニューが。
実はそれこそが「パイナップルケーキ」だったのですが、私が習ったそれは、あのパイナップルケーキとは似ても似つかない見た目&味で、まったく気が付かないままスルーしてしまいました。
というのも、中の餡はもちろん業務用の餡。たぶんひとかけらのパイナップルも使われていない、香料と色素でできた砂糖の塊のようなジャムでした。外のクッキー生地も、形も、台湾のものとは別物でした。
点心教室の生徒さんからのリクエスト
帰国後に東京ではじめた点心教室。2006年~数年続けた点心教室は人気のクラスでした。月に50名近くの生徒さんが通ってくださって、お饅頭、水餃子、焼き餃子、小籠包、生煎、パイ菓子などを作るクラスでした。
そんな折、「パイナップルケーキを作りたい」とリクエストをいただきました。そう、私もパイナップルケーキ好きだったのです。そうですね、パイナップルケーキ作りましょうね、とお答えして、いそいそと試作を始めました。
私の求めるパイナップルケーキはいずこ・・・
試作を始めたものの、パイナップルケーキを食べれば食べるほど、材料を知れば知るほど、私の中で「パイナップルケーキ」の姿がわからなくなっていきました。そもそも、パイナップルを使っていないパイナップルケーキが多かったり、パイナップルを使っていても冬瓜が必ず使われていたり、簡単にジャム状にするために寒梅粉が使われていたり。冬瓜使ったり、寒梅粉を使ったりするたびに違和感だけが大きく膨らんで、生徒さんとの約束を果たせぬまま、私のパイナップルケーキへの気持ちはすっかり冷めてしまいました。
私が納得できるパイナップルケーキはどこにあるんだろう?という疑問だけが残ったまま、迷宮入りしてしまいました。2009年ぐらいの出来事でした。
2017年、スリランカでの瞑想コースでの出会い
2017年2月、私はスリランカのヴィパッサナー瞑想センターにて30日間のコースを終えて、コース最終日に朝食を摂っていました。そこで、同じコースに参加していた台湾からの瞑想者に出会います。彼女とは中国茶の話で盛り上がり、スリランカで美味しい紅茶に出会えなかったことにお互い落胆していることを知ります。
私たちが朝食のあと、紅茶工場を改装したホテルに向かうこと、そこはもしかしたら小規模生産の手作りの紅茶を手に入れることが出来るかもしれない場所だと知った彼女は、私たちに同行したいといいました。私たちは一緒にキャンディからヌワラエリアに向かい、そのホテルで一緒にアフタヌーンティーを楽しみながら、しばらくの間中国茶について大変盛り上がりました。
彼女の誘いでその次の月に台湾に行くことになったのは自然の流れでした。私は「台湾を再訪するなら、ぜひやりたいことがある。本物のパイナップルケーキを作りたい」と彼女に告げました。彼女は素晴らしいヴィーガン料理の先生を紹介してくれると約束してくれました。
20017年3月、台湾で2日間料理のプライベートレッスンを受けました。レッスンをしてくれた王先生は、とてもチャーミングで、パワフルで、楽しい先生で、王先生の作る料理はどれもこれも美味しい。シンプルで簡単に見えるけど、先生のセンスの良さが光る、そんな料理を作る方でした。
先生はレッスンの途中でこのように言いました。「最簡単、最好吃!」
材料も作り方もシンプルなものが、
いちばん美味しい!
そう、そうなんです!!
私、この一言にものすごく自分を肯定してもらった気がしたのです。この言葉を聞いた時、私本当に涙が出るぐらい嬉しかったのです。
なぜそこまで感動したかというと、日頃私自身が感じている不安をその言葉が払拭してくれたからです。
料理をするとき、私の作るものはとてもとてもシンプルです。料理教室でお伝えしているものも、本当に簡単な、素材も単体か2つぐらいまでの組み合わせのものが多い。
見た目もとてもシンプルです。
だから時々、不安になるんです。
みなさん満足してくれてるのかな?って。私自身はこれが一番美味しい!って思って紹介しているのだけれどね。
たとえば麻婆豆腐。
肉を料理しなくなって、ベジタリアンバージョンの麻婆豆腐の試作を重ねてたとき、最初はもともと使っていた牛肉の旨味を出すために代わりに何を使えばいいか?試行錯誤していました。
また、コクを出すために油もピーナッツ油やゴマ油、ねぎ油を作って試してみたりといろいろなことをしました。
でも、最終的にこれだ!となったレシピは何も特別なものは使わない作り方。
ただし、ベジタリアンバージョンの麻婆豆腐では、素材の下ごしらえや、調味料を入れるタイミングなどが最終的な味に大きな違いをもたらすことを知りました。
野菜だけで美味しく満足感のある料理を作るには、肉や魚を使う時よりも繊細なバランス感覚ときめ細かい手順が必要な気がします。でもそれは必要性を感じれば誰でも出来ること。
例えば野菜を炒める時にほんのひとつまみの塩を入れて炒めると美味しさが違うと自分自身で実感出来れば、これから料理する時にひと塩振るようにすることぐらい誰でも出来るはずです。
シンプルな料理はどんどん自分の感覚を敏感にしていきます。使うものが少ないからこそ、ひとつひとつの素材の味が大切だし、調味料も大事。それを入れるタイミングが味にもたらす違いもわかるようになります。
台湾の先生が最初におっしゃった
最簡単、最好吃!は、
ただ簡単な料理が一番、ということではなくて、先生は素材を厳選し、調理法を熟慮し、最小限の手数で美味しさを創っていたのです。
私は、先生と完全に同じ考えです。お会いするまで先生のことは全然存じあげなかったし、先生の作る料理を食べたこともなかったのだけれど、最初にその言葉を聞いた時、この方の作るものに私は全く違和感を感じないだろうとすぐにわかりました。
そして、先生が作るものは、どれも私たちにとって自然に美味しいものでした。
パイナップル100%の餡
パイナップルケーキを作るレッスン。先生は当然のようにパイナップルの頭を落とし、皮をむくところからレッスンを始めました。パイナップル100%の餡づくりです。ヴィーガン仕様のクッキー生地はもちろんバターやチーズは使いません。パイナップルの風味を最大限に楽しめます。
当たり前ですが、冬瓜も寒梅粉も使わない。クッキー生地はバターもチーズも粉乳も使わない。もちろん卵も入っていません。
余計な味せず、私はパイナップルよ!という美味しさを引き立てるクッキー生地。なるほど、という味でした。
私はこれを作るようになってから、パイナップルケーキがなぜ台湾で作られるようになったか?というストーリーを読みました。
熟したパイナップルが売捌ききれず、山積みになってしまいどうにも困った産地の方たちが考えて作ったのが台湾でパイナップルケーキが作られるようになった理由だそうなのです。
だから、パイナップルを使う量を減らす目的で冬瓜を入れるというのはそもそも発祥の理由と相容れないし、いちばんのポイントはパイナップルの美味しさなんですよね。クッキー生地はあくまでもパイナップル餡と調和して邪魔しない、むしろパイナップルという主役を引き立てる存在。
2008年当時、いろいろと試作しながらもどうしても前に進めなかった理由。
それは、私がこの「パイナップルケーキ発祥の意義」を理解していなかったということ。
そしてそれ以上に大事な理由は、先生に会って、そして力強い最簡単、最好吃!を聞いて、私は私のままで良いと自信を持つため。
こんな、長〜い長〜い時間をかけてやっと進んだ私のパイナップルケーキ。先生に教えていただいたものを少しだけアレンジ。でもあっけないほどシンプルなのは変わりません。
点心のクラスでパイナップルケーキをやるのを長〜い間待っていてくださったみなさん。
こんだけ時間かかってこんなにあっけないの?と言われそうですが、そう、これが私のパイナップルケーキです!
時間をかけてようやく私の中のパイナップル🍍ケーキが熟したようです。
沖縄の有機パイナップルをつかった、日本人好みのパイナップルケーキ

完熟のパイナップルを冷凍したものを使って作る餡。琺瑯の鍋でひたすら煮詰めていく作業は、信博さんの担当。簡単な作業ではありません。汗だくになるし、火傷の心配もいつもつきもの。
そんな苦労の末に出来上がる餡を使って作っています。
パイナップルの風味をさらに引き立てるには?と考えて作ったのがパッションフルーツピュレ入りのパイナップルケーキ。
どちらも甲乙つけがたい美味しさです!ぜひお茶のお伴にしていただけたら嬉しいな♪